定員:10名
期間:2026年5月〜2027年3月
日時:毎週土曜日 18:30〜21:30(毎月第三週は日曜日13:00〜17:00)
学費:330,000 円 教程維持費:11,000円(年額)
開催教室:本校

日本画を学ぶということは、素材や技法を習得することに留まらず、絵画原理を探究することです。しかしながら現在は、美大での日本画教育が一般的であり、課題から自由制作へ至るカリキュラムは画一化されたものとなっています。
かつて日本画を学ぶ場では、小規模な塾制度の中で日々修練を重ねていました。時代背景こそ異なりますが、現代に応用することは可能なはずです。
本講座では、自立した作家として歩み出せるように、課題に真剣に取り組むだけではなく、さらに実践のための可能性を探究し続けます。具体的には個別の面談に始まり、作画意識の確認をします。その後は毎回講義と実践がスタートすることになりますが、内容は基礎素材論(支持体、描画材、色材等)に始まり、技法や模写についても習得の方法を探っていきます。他には写生や下図などの、絵画制作に必要な準備の方法を習得するために、古典から現代までの作家や作品研究をゼミ形式で随時開催します。
教室での制作時間は限定されますが、毎月講評会を開催します。ここでは講師が一方的に語るのではなく、作者は作品についてプレゼンを行い、参加者全員がディスカッション形式で意見を述べ合います。
超・日本画ゼミでは、今の時代を作家として生き抜くために、あえて超という言葉を付けました。飛躍のためには徹底した探究が必要です。経験、未経験は問いませんので、やる気のある方は是非参加してください。
間島秀徳
超・日本画ゼミは、「あなた」の美のための現場です。ここでは、あなたがどのような人で、何をしたくて受講しているのか、ということを大切にしています。日本画にまつわる素材・技法、歴史・理論の知識、日本画をはじめとする絵画経験を問わないのは、描くための知識・方法とはそもそも個人的な検討が必要であり、超・日本画ゼミはその地点からともに考えることを重視しているからです。そのためには、自他を見つめることが必要であり、その過程に、知識の学習・取得、未知の方法の実践・練習、同じゼミ生とのディスカッション、はたまた遠方への遠足・合宿があります。不思議に思われる人も多いですが、超・日本画ゼミは、必ずしも毎回描く時間を設けていません。講師とゼミ生が、自分自身を超えようと「描くこと」「考えること」「知ること」を通して切磋琢磨する絵画の現場——それが超・日本画ゼミです。
小金沢智
超・日本画ゼミでの体験を通して、ご自身の核となる「何か」に触れてほしいと強く思います。
日本画というキーワードから日本画材という材料にいたるまで、皆さんがこのゼミに興味を持ったきっかけは多岐に渡っていることでしょう。中には「なんとなく気になったから」受講してみようと思っている方もいるはずです。この、「なんとなく」という感覚を本当に大切にしてください。ささやかで見過ごしてしまうほど小さな興味関心が、作家として歩んでいく旅路への招待状なのですから。
私は2年間に渡り、超・日本画ゼミに受講生として在籍しました。美大を出てから何年も模索する中、作家として確かな軸を構築するきっかけをくれたのが他ならぬこの場です。受講していなかったら、今の私は確実に存在していません。
ぜひ、気軽に門戸を叩いてみてください。私達は皆さんの旅路を精一杯サポートします。
香久山雨
授業内容

【基礎素材論】
- 支持体(和紙、布、板等)
- 描画材(筆)
- 色材(岩絵具、水干、アクリル等)
- 接着剤(膠、アクリル樹脂等)・墨、硯
【制作(個別面談随時)】
- 講評会(毎月開催)
- 写生、下図研究
【古典絵画から現代絵画まで】
- 技法(水墨等)
- 模写(臨写他)
- 作家研究
- 作品研究
- 読書会
- 修了展
【客員講師予定】
- 美術評論家
- 美術館学芸員
- 美術史研究者
- 伝統職人
- 現代作家
【研修】
- 美術館、博物館見学
- ギャラリー見学
- 筆工房、紙漉き工房見学
- 古美術研修(国内、海外)
- 自然研修(海、山)
講師プロフィール
間島秀徳

1960年茨城県生まれ。1986年東京藝術大学大学院美術研究科日本画修士課程修了。2000~2001年フィラデルフィア、ニューヨークに滞在。水と身体の関わりをテーマに、国内外の美術館から五浦の六角堂、二条城、清水寺、泉涌寺、大倉集古館に至るまで、様々な場所で作品を発表。現在、武蔵野美術大学日本画学科教授。
小金沢智

キュレーター。東北芸術工科大学芸術学部美術科日本画コース准教授、美術館大学センター研究員。1982年、群馬県生まれ。2008年、明治学院大学大学院文学研究科芸術学専攻博士前期課程修了。専門は日本近現代美術史、キュレーション。世田谷美術館(2010-2015)、太田市美術館・図書館(2015-2020)の学芸員を経て現職。「現在」の表現をベースに据えながら、ジャンルや歴史を横断するキュレーションによって、表現の生まれる土地や時代を展覧会という場を通して視覚化することを試みている。
香久山雨

1989年東京生まれ。2013年東京藝術大学絵画科油画専攻卒業。2017年度、2018年度超・日本画ゼミ受講。芸大の油画専攻に進学するも、「日本人としての肉体を持って生まれた以上、日本の美術、芸術のことを知らないまま画家になることはできない」と感じ、卒業後は日舞や能の勉強に勤しみながら美学校の超・日本画ゼミで学ぶ。2020年以降、絵画教室を主宰しながら墨絵を軸に作品発表を行っている。
講師インタビュー

2012年に間島秀徳さんを講師に迎えて開講した「超・日本画ゼミ(実践と探求)」。その後、2016年に小金沢智さんが、2018年に後藤秀聖さんが講師として加わり(後藤氏は2023年6月をもって退職)、2024年からは香久山雨さんを新たな講師として迎えます。かつては受講生として「超・日本画ゼミ」に通った香久山さん。当時を振り返りながら、「超・日本画ゼミ」のこれまでとこれからについて語っていただきました。
「日本画をやろう」と思って
香久山 「超・日本画ゼミ」に入ったのは2017年です。もともと大学は油画専攻でしたが、3年生ぐらいから、現代美術や油絵具を使って絵を描くことに疑問を抱くようになりました。私はスペインの画家アントニオ・ロペスがすごく好きなんですが、彼の作品の中にスペイン市場で売られているウサギの肉塊をボンッと置いて淡々と描いた絵があって、一度自分もその状況を真似して描いてみようと思ったんです。それで、 かろうじて手に入った丸鶏を2週間くらいかけて描きました。しかし、全然ロペスにならないわけです。対象をちゃんと見て描いているし、細かく描いてもいるけど、スペインと日本ではまず圧倒的に光が違う。それに私は日本人の肉体を持ってるから、ロペスの肉体とは全く違う。描くことで遺伝子レベルの違いを感じました。
そこで、自分はこのまま油絵具やアクリル絵具を使い続けていいのだろうか?という疑問が生じたんです。結局その疑問は拭えないまま大学を卒業してしまいました。ただ、卒業後も肉体への関心は続いたので、人の身体に直接触れる仕事をしたいと思い、エステサロンの経営をはじめました。そうして紆余曲折あって日本画を習いたいと思うようになり、「超・日本画ゼミ」を受講したんです。
「『超・日本画ゼミ(実践と探求)』を受講して」

美学校「超・日本画ゼミ(実践と探求)」(講師:間島秀徳+小金沢智+後藤秀聖)は、今の時代を自立した作家として生き抜くために、実践の可能性を徹底的に探求する講座です。小規模な塾制度において日々修練が重ねられていた、かつての日本画の習得の場を現代に応用し、基礎素材論、模写、古典から現代までの作家研究などをゼミ形式で開催します。本講座で学んだ受講生にとって「日本画」とは何なのか。なぜ「超・日本画ゼミ」を受講したのか。お話を聞きました。
Q1. 美学校を知った経緯を教えてください
知人から教えてもらって知りました。当時は、地元の群馬で事務員として働いていたんですが、元々絵を描くのが好きで、ずっと絵を描きたいと思っていました。ちょうど職場の契約が切れるタイミングで美学校を教えてもらったので、いい機会だし仕事を辞めて上京しました。美学校には何回か見学に来て、事務局のスタッフの方や校長先生とも話をして入校を決めました。
レポート「FUSION〜間島秀徳 Kinesis/水の宇宙&大倉コレクション〜」展

ホテルオークラに隣接し、サントリーホールや虎ノ門ヒルズからもほど近い大倉集古館。現在、同館で「FUSION〜間島秀徳 Kinesis/水の宇宙&大倉コレクション〜」展が開催されています(〜2021年8月15日)。展示されているのは、当校「超・日本画ゼミ」講師・間島秀徳氏の作品と、大倉集古館のコレクション。間島氏が「水の変成」をテーマに描き続けてきた《Kinesis》連作を中心とした近作と、中世から近代の古典美術を併置する異色の試みです。・・・続きを読む
過去の修了展など
授業見学お申込みフォーム
授業見学をご希望の方は以下のフォームに必要事項を入力し送信してください。担当者より日程等のご案内のメールをお送りいたします。
*ご入力いただいたお客様の個人情報は、お客様の許可なく第三者に提供、開示することはいたしません。
*フォーム送信後3日以内に事務局から返信のメールが届かなかった場合は、フォームが送信できていない可能性がありますので、お手数ですが美学校事務局までご連絡ください。
〈絵 画〉
▷授業日:毎週土曜日13:00〜17:00
モノ(事柄)を観察し考察し描察します。モノに対する柔軟な発想と的確な肉体感覚を身につけます。それぞれの「かたち」を模索し、より自由な「表現」へと展開する最初の意志と肉体の確立を目指してもらいます。
▷授業日:毎週水曜日18:30〜21:30
細密画教場では目で見たものを出来るだけ正確に克明にあらわす技術の習得を目指します。この技術は博物画やボタニカルアート、イラストレーションなどの基礎になるものです。
生涯ドローイングセミナー 丸亀ひろや(+OJUN+宮嶋葉一) 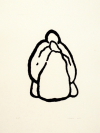
▷授業日:毎週木曜日 18:30〜21:30
Drawing「線を引く。図面」などを意味します。美術の世界では、紙などに鉛筆やペン、水彩などで描かれた表現形式を言います。描ける材料ならどのような画材でも持参してください。毎回ドローイングの制作を行います。
▷授業日:毎週土曜日18:30〜21:30(毎月第三週は日曜日13:00〜17:00)
本講座では自立した作家として歩み出せるように、制作実践のための可能性を探究し続けます。内容は基礎素材論に始まり、絵画制作に必要な準備の方法を習得するために、古典から現代までの作品研究等をゼミ形式で随時開催します。
▷授業日: 昼枠 毎週木曜日13:00〜17:00/夜枠 毎週木曜日18:00〜21:00
油絵を中心としながらも、アクリル絵の具、水彩なども含めて幅の広い表現を試みていきながら素材自体も自分で選んで絵を描いていきます。絵を描くのと同時に「私は何故絵を描くのか?」と「どのような絵を描きたいのか?」の両方を考えながら絵に向かっていきましょう。
テクニック&ピクニック〜視覚表現における創作と着想のトレーニング〜 伊藤桂司 
▷授業日:毎週月曜日 19:00〜22:00
グラフィック、デザイン、イラストレーション、美術などの創作における技術の獲得(テクニック)と楽しさの探求(ピクニック)を目的として、シンプルながら多様なアプローチを試みていきます。
▷授業日:隔週金曜日 13:00〜17:00
本講座では絵画を起点に今一度美術の在り方を考えます。全体を変えることはできなくとも自分なりの価値基準の物差し、あるいは持続可能な活動の下地をつくることはできるかもしれません。制作だけでなく座学、個人面談などを通して総合的に絵画に紐づくあれこれを探求します。
▷授業日:隔週水曜日 13:00〜17:00
この講座では、技術を1から教えるのではなく、それぞれの絵をどう面白く展開していくかを探っていきます。基本的には油彩で描きたい絵を自由に描いてもらいますが、時には課題やテーマを決めて描くこともあるかもしれません。放課後の部活のように絵を描き、話をしていきましょう。





