哲学者・荒谷大輔さんが講師を務める「アートに何ができるのか〜次に来る『新しい経済圏』とアーティストの役割を考える」(以下「アートに何ができるのか」)。著書『資本主義に出口はあるか』などで、新しい経済圏の形を提示するだけでなく、実際に新たな「国家」の創造に取り組むなど、実践的哲学者として活動する荒谷さん。本講座でも、私たちの日常生活圏を問い直しながら、アートが果たせる役割について実践的に探求していきます。本稿では、幼少期の哲学的体験にはじまり、自身と社会との関係の変化など、荒谷さんの活動と講座の背景についてお話しいただきました。

荒谷大輔(あらや・だいすけ)|慶應義塾大学文学部教授。専門は哲学/倫理学。主な著書に『資本主義に出口はあるか』(講談社現代新書)、『ラカンの哲学:哲学の実践としての精神分析』(講談社メチエ)、『「経済」の哲学:ナルシスの危機を越えて』(せりか書房)、『西田幾多郎:歴史の論理学』(講談社)、『ドゥルーズ/ガタリの現在』(共著、平凡社)など。
哲学的な原体験
出身は、宮城県仙台市です。仙台市中心部から電車で数駅先の郊外で育ちました。父親は普通のサラリーマンで、どちらかと言えば、資本主義社会の中でお金を稼ぐタイプだったと思います。小学校は徒歩20分かけて通っていたんですが、小学2年生の通学途中に、突然、言葉と意味の関係が分からなくなったことがありました。道路を走る車を見て「ロールス・ロイス」という言葉が浮かんだのはいいのですが、その言葉が現実に見た車とどうつながるのかがわからなくなったのです。そこを起点にどんどん世界が崩れていく感じがありました。今、自分が立っている地面が本当に地面なんだろうかと。言葉と意味との関係がズレて、足元がぐらぐらする感じです。すごく不安になって母親に「ロールス・ロイスがなんなのか分からなくなった」と言ったものの、相手にされなかったですね。しばらくしたら治りましたが、哲学的な原体験として記憶しています。
高校時代に、生物が無機物から有機体に変化していく過程に興味を抱いて、大学では理科系の学部に進学しました。今思うと、それは哲学的な興味によるものですが、当時は自分の関心は生物物理の分野に該当すると思ったんです。でも、入学して早々にその判断は誤りだったと気づきました。大学では、ひたすら実験を行いますが、理論に一致した実験結果が出るまで教授が許してくれないんです。理論と一致しないのは、単に僕の実験のやり方が間違っただけなわけですが、でも、もしかしたら新発見の可能性だってあるじゃないですか(笑)。頑張って理論に合わせた結果を出すための実験を繰り返すうちに、自分が何をやってるのかわからなくなってきて、1年生の途中で大学に行かなくなってしまいました。
大学をドロップアウトしてからは、友人と出版社をはじめて、書店営業をやったり、それまで小説を真面目に読んだことがなかったにも関わらず、自分で小説を書いたりしていました。小説のあとがきとして、当時自分が考えていたことを書いた文章があるのですが、今思えばそれは哲学的な問いでした。それで、このまま出版社を続けるのはやめて、大学に戻って文転して哲学を学ぶことにしました。現在は、フランスの精神分析家ジャック・ラカンの研究をしています。
一般的に「哲学研究」と言うと文献を読み込みますが、ただ哲学書を読むだけでは、研究者の自己満足ではないかという疑問が昔からありました。文献を読むことで世界観をひっくり返すわけですが、それが自分の中だけで終わるのではなく、社会の枠組みを変えるところまで至らないと意味がないと思っていたんです。とは言え、実際にそれをどうやるのかは手探り状態で、しばらくは文献研究の成果発表を重ねていました。今の社会の枠組みをいかにひっくり返すかを理論として扱いながら、実際に自分の実践としても行いはじめたのは、ここ10年程の話です。

「見て伝える哲学」としての舞踏
美学校には、生西康典さんが講師を務める「実作講座『演劇 似て非なるもの』」の修了公演にゲストとして呼んでいただき、ソロで踊ったのがきっかけで関わりはじめました。大学院生の頃から、自己流で暗黒舞踏をやっていて、あるとき生西さんが僕の踊りを見て声をかけてくれたんです。僕としては、舞踏も哲学の実践として考えています。この社会で生きている私たちの身体には「社会的なコード」が染み込んでいて、そのコードによって行動が形づくられています。そのコードを一度解体して別の形に組み直していくことを、僕は「ゼロ地点」と呼んでいます。踊りは「ゼロ地点」に立ち返ることで、言わば「見て伝える哲学」として位置づけています。
「アートに何ができるのか」は、まずは「アート」がどのように評価されてきたのかを歴史的に振り返りながら、ある意味、偶然的な歴史に規定されている現行社会の枠組みを外してなお「アート」として機能し得るものは何かということを受講生の皆さんと議論していきます。資本主義経済のなかでは、どのようなアートが評価されて、その評価のロジックはどのように成り立っているのか。さらに言えば、それより前に教養主義の文脈があって……と、歴史的な文脈をたどりながら、そこに働いているウソやごまかし、幻想を排除していった先に、ポジティブさを見出せるアートがあるのかどうかを考えていくわけです。
僕自身は、オルタナティブな経済圏において、人と人とをつないでいくためのキーとしてアートを位置づけられるのではないかと考えています。ですが、僕が議論を誘導するのではなく、受講生同士のディスカッションを通して「アートとはこういうものである」といった考えを共有していきたいと思っています。そもそも、美学校自体がオルタナティブな場であり、講座を通して人がつながって、ゆるい関係性が結ばれていると思うのですよね。その「ゆるさ」が素晴らしいと思い、この場所で講座をやらせてもらいたいと思ったのでした。

アーティストの「個人主義」を乗り越える
今期の受講生には、日頃から作品制作をしているけど、作品や制作について言葉で話すのは初めてという方もいます。なかなかうまく話せないけど、すごく刺激的だとおっしゃっていました。一年間の学期の終わりには作品をつくって発表してもらうのですが、その過程で「アートとは何か」という問いの答えをクラスで緩やかに共有し、共通の認識をベースに互いの作品について語り合うことができる環境を作ります。もちろん「こうでなければアートではない」という枠をはめるのではありません。それまでのディスカッションの中で共有された事柄を使って、互いの作品を通りいっぺんの言葉以上に深堀りしていくことが目標です。
思うに、アートの業界も「個人主義」に侵されていると思うんですよ。「オリジナリティ」を発揮して、個々人の業績を積み上げていかなければならないと考えられている。どこの業界もある程度まで同じだと思いますが、その前提って、まったくもって資本主義の枠組みにほかならないのですよね。そうした枠組みから自由になれるのがアートのひとつの特権であるはずなのに、アーティストもまたその枠の中で社会的な評価を得ようとする傾向があるように思います。
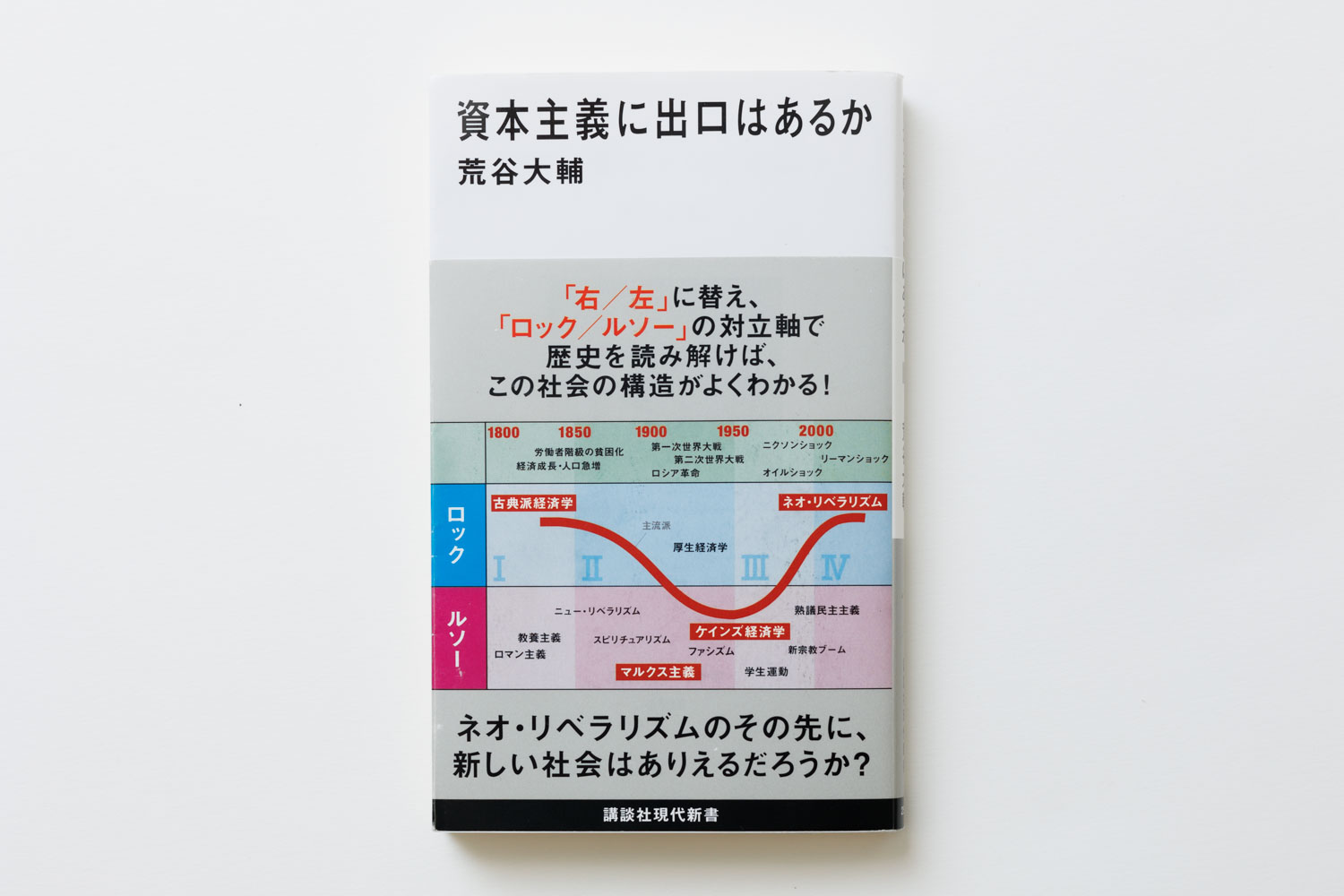
荒谷大輔『資本主義に出口はあるか』(講談社、2019)
他者からの理解を煙に巻いて「独自性」を謳うのがアーティストの仕事だとすれば、ディスカッションで共有された事柄で互いの作品について語り合うことなんて、余計なことというか、営業妨害にすらなりうるかもしれません。でも、創造される作品の「価値」を、「今これが流行っている」とか「最近の批評家が注目しているのは」とか、外側から価値基準を輸入して判断するのではなく、内在的な議論の中である程度客観的に共有していくことは、非常に重要なことだと思います。作品を作る作業としても、作家が個人でリスクを全部引き受けてマーケットの審判を問うみたいな厳しい状況にさらされずにすみます。
そのためにも、特定の社会の枠組みから離れても「価値」をもちうる作品をすでに制作されているアーティストの方にゲスト講師として来てもらい、実際にどのようにすれば「アート」なるものができるのか、制作過程について深堀りするようなお話をしていただいています。今期は飴屋法水さん、生西康典さん、川口隆夫さんにゲスト講師としてお越しいただきました。僕は作家ではないので、技術上の具体的なアドバイスはできないのですが、受講生の話を聞きながら一緒に作品を深堀りしていくことはできると思います。作家として制作をしていて、自分の制作や作品を自覚的に位置づけてみたい人や、批評家を目指している人にも受講をお勧めできるでしょうか。もちろん、作家ではない方も歓迎です。

「死ぬ」ところからはじめる
2022年に「ハートランド」という新たな「国家」をつくるプロジェクトを立ち上げました。資本主義とは別の経済圏を資本主義と並行的に作っていこうというプロジェクトです。興味がある方には、まずDiscordというチャットサービス内のコミュニティへの参加をお願いしているのですが、現時点で700名を超える方々が参加しています。新しい国をつくると言っても、既存の国を否定するという意味ではありません。近代国家とは別の意味での「国」を作るという感じです。だから、今ある国家とは対立関係にはならないと思っています。興味のある方は、ハートランドのウェブサイト( https://heart-land.io/ja/ )を見ていただけたらと思います。
僕は、生来どこか諦めがあるというか、社会と距離のある人間で、小学生のときのあだ名は「仙人」でした(笑)。実際に2014年ごろまでは、自分の「社会的な身体」が社会のコードに固有のロジックに絡め取られていることを認識しつつ、そうした自分自身と距離をとるような生き方をしてきたと思います。僕の場合で言えば、大学教員という枠組みの中で生きていくということですが、哲学的なことを考えるのは、そうした社会的な身体から離れるための行為で、哲学研究をしている分には非常に楽しかったのですが、そうした営みと社会的な身体との間には、まだまだ断絶があったと思います。

ただ、2014年ごろに、個人的な理由で精神的にすごく落ち込んだことがあって……そのときに死のうと思ったんですね。自殺も割と本気で考えていましたが、それはそれで欺瞞だなと思って、なんとか真剣に「死ぬ」をやろうと思っておこなったのが、舞台に立って踊ることでした。それまでも実は哲学の実践の試みとしてダンスのトレーニングは受けていました。社会的なコードは身体に蓄積するので、哲学者としてそれらをきちんと相対化するためには、自分の身体を掘り返さなければならないと思ったのです。ただ、その文脈では舞台に立つ必然性はありませんでした。哲学研究の一環として自分の身体を材料にするわけなので、他人に見せて評価されることはまったく眼中になく、むしろ、社会的なコードにがんじがらめになっている身体の格闘を見て、誰が喜ぶだろうかと考えていました。ですが、「死ぬ」って、つまりはそういうことだなと思ったんです。他者の視線が振りかけられる社会的な秩序の中で、そのコードを解体することこそが、まさに「死ぬ」ということじゃないかと。
我々が「生」と呼んでいるものは「社会的な生」で、我々は自分の存在を何かの枠組みによって意味づけて生きています。社会的な生とは別に、生物学的なレベルでの生があるので、社会的に死んだからといって、生きているじゃないかと言う人もいると思うのですが、生物学的な生を「自分」と考えることはできないんですよ。生物としての存在は「自分」というよりも、環境の一部というべきで、環境から切り分けられた「個体」を定義するのは生物学的にもそれなりに難しいとされています。何らかの仕方で「個体」を定義できたとしても、その「個体」は単に遺伝子を運ぶための媒体に過ぎないとも考えられるわけです。いずれにせよ、「自分」というのは社会関係の中で確立しているもので、その「自分」の解体を自分の部屋の中でひっそりやるのではなく、他者の前で実際の社会関係に影響を与えるものとして行うことで、「死ぬこと」をきっちりとやれるのではないかと思ったんです。
やってみると、そんなものを観せられる方はたまったものではないと言われるかと思いきや、破格の評価をしてくれる人もいたりして、自分の中で社会的実践の手応えがつかめた気がしました。ハートランドのプロジェクトは、これまでの社会関係を相対化して別なかたちで組み上げようとしているのですが、そうしたことも単に理論的な可能性としてではなく、現実の社会に実装できそうな感触があります。「自分」という存在を社会関係の中で解体することが、他者にとっても意義をもつことが確認できたことで、自分と社会との距離がぐっと縮まり、他者と一緒にゼロから新しく何かを作り上げることのリアリティが感じられるようになりました。そういうわけで、最近は毎朝「死ぬ」ところから一日をはじめることを心がけて生活しています。
2022年10月25日 収録
取材・構成=木村奈緒 写真=皆藤将
授業見学お申込みフォーム
授業見学をご希望の方は以下のフォームに必要事項を入力し送信してください。担当者より日程等のご案内のメールをお送りいたします。
*ご入力いただいたお客様の個人情報は、お客様の許可なく第三者に提供、開示することはいたしません。
*システム不具合によりフォームが正しく表示されない場合がございます。その場合はお手数ですが、美学校事務局までメールか電話でお申込みください。
*フォーム送信後3日以内に事務局から返信のメールが届かなかった場合は、フォームが送信できていない可能性がありますので、お手数ですが美学校事務局までご連絡ください。
アートに何ができるのか〜次に来る「新しい経済圏」とアーティストの役割を考える 荒谷大輔 
▷授業日:隔週火曜日 18:30〜21:00
この講座では、まず現在アートがおかれている社会的な状況を振り返って考えながら「アート」と呼ばれるものの本質を明らかにします。参加者が知らないうちに身に着けている価値観の前提を問い直しつつ、それでも直観的にはおそらく各人が捉えているアートの本質を、ディスカッションの中で明らかにしていければと思います。